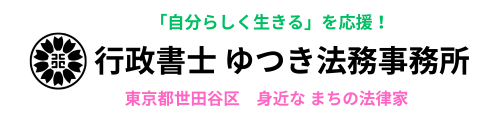「いま」と「将来」の暮らしを守る支援の詳しい内容をご紹介します。
✅ 法的手続き(代理権)ができる契約一覧
| 契約名 | 代理権の有無 | 主な対象手続き | 発効条件 |
|---|---|---|---|
| 任意代理契約 (財産管理契約) | ✅ あり | 日常の事務手続き (役所・銀行・介護契約など) | 契約締結後すぐ |
| 任意後見契約 | ✅ あり | 判断能力低下後の財産管理・医療契約など | 家庭裁判所の審判後 |
| 家族信託契約 | ✅ あり | 財産の管理・承継 (不動産・預金など) | 信託契約締結後 |
| 法定後見制度 (成年後見・保佐・補助) | ✅ あり | 判断能力が著しく低下した場合の包括的支援 | 家庭裁判所の申立てと審判 |
※行政書士は、行政書士法や他士業の法律で禁止されている行為はできません。
必要な場合は、お困りにならないよう、司法書士や弁護士等をご紹介いたします(紹介料:無料)
| 用語 | 意味・範囲 |
|---|---|
| 任意代理契約 | 本人の意思で代理権を与える契約。 財産管理に限らず、医療・介護・生活支援なども含められる。 |
| 財産管理契約 | 任意代理契約の中でも、財産に関する事務手続きに特化した契約を指します。 銀行口座の管理 公共料金・税金の支払い 不動産の賃貸・売却手続き 年金や保険の手続き などが対象 |
🌱 見守り契約 任意代理契約 任意後見契約
| 契約名 | 主な目的 | 効力発生時期 | 代理権の有無 | 裁判所の関与 |
|---|---|---|---|---|
| 見守り契約 | 定期的な連絡・訪問で生活状況を把握 | 契約締結直後から | なし(助言のみ) | なし |
| 任意代理契約 (財産管理契約) | 判断能力があるうちに事務手続きを委任 | 契約締結直後から | あり(範囲を指定) | なし |
| 任意後見契約 | 判断能力が低下したときの法的支援 | 家庭裁判所の審判後 | あり(広範囲) | あり(監督人が就任 |